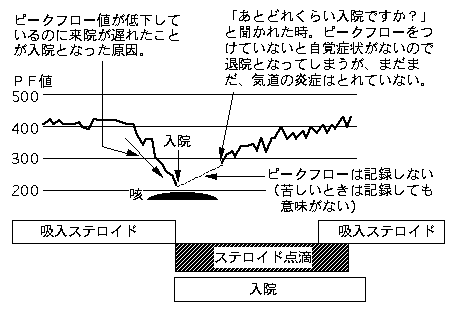
「発作の時はカリン入りの飴でもなめてろ」と主治医から。
私こと、平成4年2月風邪が長引き、かかりつけの病院で、
「気管支喘息になったね」
と言われた。週に一度診察を受けるようになり、この頃からすぐに風邪を引きやすくなり、時にはピーピーとなり、小さな点滴もしていただき、おさまって帰るといったことが3年ぐらい続いた。
平成7年6月、この日も病院に行き、少し風邪を引いて咳が出て、この時も小さな点滴をしていただいて帰宅したのだった。しかし夜11時過ぎ息苦しくなりヒーヒーとなって布団を4つに折って伏せていたのは覚えているが、すぐ後にひどい発作をおこしてしまった。家族の人達がまだ起きていたので気が付いてくれて、いつもと違った息苦しさのようで変だと思い部屋に来てみてくれたら、もう顔がどす黒くなって仰向けになって、手は上にあげたままだったとの事。すぐに救急車を呼んで某総合病院に運ばれた。私が気が付いた時には翌日の午前10時を過ぎていたとか。話によるとあと5分遅かったら死にいたるところだったとか…。救急車の中で酸素をしたのもよかったのではないかと言われた。この時は3週間で退院した。
しかし、退院をして6日目の朝早くまた軽い発作をおこしてしまった。すぐに総合病院に電話をし、家の車で送ってもらい、点滴をしていただき、その時は30分位でおさまった。ところが、私が前にお世話になった先生が泊りでいるから呼んでおいたので、おいでになるまで待つように言われた。先生は間もなく来て下さって、顔を見るなり、
「このまままた入院しなさい。今度は24時間の点滴をするからそのつもりで」
と言われ2回目の入院となった。部屋は6人部屋だった。1本6時間かかり、それを4本夜昼通して行った。もうトイレに行くのにも顔を洗うのにも台の付いたのに点滴をづるづる引っぱって歩いた。先の入院の時は点滴は1日2本で終わっていたのに、自分では今回は前より発作も軽いように思うのだが…。4日目頃から湿疹が体全体に出て、かゆくてかゆくてむくみもあって、先生の廻診の時に話したら、
「これは仕方がないんだ。塗り薬を出すからそれを塗れ」
と取りつく島もない。喘息よりもかゆみとむくみで苦しく、本当に頭がおかしくなってしまいそうだった。今でも思い出すと、ざわざわする思いだ。私のようなものは点滴の中にはどんな薬が入っているのかわからないし、飲み薬だって《これを飲みなさい》と言われればそれが私の体には効くのだと思うしかない。患者は医師のことを信用し、それに従うしかないと思うのです。
それから3日後、
「皮膚科に行って診察を受けるように」
と言われた。ところがこの総合病院には週に1度火曜日でないと診察ができないとのことでその日を待った。火曜日になり診察を受けたところ、
「これは大変なことだ。薬害を起こしているからすぐに内科の先生に話して点滴も薬もとめてもらって検査を受けなさい」
とのこと。すぐ先生の廻診の時にお話ししたら、
「そんなはずない。おまえの体がアレルギー体質に変わったのだから」
と言われ、このまま点滴も薬も続けられてしまった。1週間後、もう一度皮膚科で診て頂くように言われ、点滴をずるずる引きずりながら下へ降りて行って診て頂いた。
先生は私を見るなり、
「何だ、まだ点滴をしていたのか。これはひどい」
と話されたので、
「どうか先生のほうから主治医の先生にお話をして下さい」
とお願いしたら、
「カルテに書いてあるのにどうして…」
と独り言のように話された。
もう24時間の点滴は4週間にもなる。心臓のほうもおかしい。苦しくて胸のあたりもむくみでパンパン。先生の廻診の時、
「こんなに苦しくてどうしたらいいのですか?」
と尋ねたところ、その日の夕方になってやっと、
「血液をとって検査をするから」
と言われた。
5日後、廻診の時先生は急にやさしくなって、
「検査の結果、やはり薬があわないのがあるから1本に減らすから。また1週間たったら体全体の検査をはじめるから」
と言われた。いろいろ検査をした結果、
「心臓が少し悪く、大動脈がボロボロだ。血圧も高いし、胃潰瘍も少し悪い。入院が少し長くなるが心臓の方少し落ち着くまでだから」
と。私も困って、
「どうすればいいのですか?」
と聞いてみたら、
「死ぬしかないだろうな」
と笑いながら話す。私も聞き方が悪かったとは思ったが、医師らしくない返事が返ってきて本当にがっかりしてしまった。点滴は1日1本になってから、かゆみもむくみもとれ体は楽になってきた。ところが、また咳が出るようになったので先生に話すと、
「喘息になってもおまえには合う薬がないから、咳や痰が少しぐらいでても、売店からでもカリン入りのあめ玉でも買ってなめてろ」
と言われてまたがっかり。そのうちヒーヒーとなりだしたので、家へ電話をしてハチミツ入りのカリン漬けを持ってきてもらって何本となく飲んだ。廻診に来ると、
「喘息持ちは咳と痰が出るのは少しぐらい仕方ないなあ」
と話す。こんなことでは今まで入院して何をしていたのだろうと思ってしまう。
「かえって体をこわすようだね」
と部屋の皆さんもびっくり。7月〜11月15日まで入院をしていた。とても辛かった。
平成7年11月、退院の日に知り合いから、
「近くの病院に喘息に明るい先生が大学病院から週に1度だけおいでになって診て下さるよ」
と聞かされ、翌日がその日だったので診察を受けた。それが今の先生でした。前の病院であったことをお話しし、自分ながらたぶん、《これは厄介な患者が来た》と思ったのではとびくびくしながらもお世話になった。
初めての日も点滴をし、少し飲み薬もいただいたように思う。終って家へ帰ったのが7時頃。ところが夜9時過ぎ頃から湿疹が出てかゆみもあったので、すぐ病院に電話でお話ししたところ、今夜は先生が泊りでいるからすぐに来るようにと言われて、湿疹のでているところを診て頂いた。
この日から吸入ステロイドやピークフローを使い始めた。吸入ステロイドを使うようになって1週間目、だんだん体が楽になってピークフローも380〜400ぐらいまで上がるようになり、先生の診察の時、
「このまま良くなるといいね」
と言われて安心して帰った。
ところが、しばらくした12月5日にまた風邪を引いてしまった。家族の誰かが風邪をひくと必ずうつってしまう。その日も先生の診察日なのだが、前の夜からヒーヒーいっていたので早目にと思って午前中にその病院の院長先生に診てもらい、点滴をしてもらい、また風邪薬を飲むようにと出してもらった。ところが、お昼頃家へ帰ってその薬を飲んで休んだところ、また湿疹が体中に出たので、午後からの先生の診察を受けた。
「もう薬は飲めないから点滴をするしかないね」
と話され、1週間点滴を続け1日1日良くなっていった。こんな時はピークフローが一番確かではっきりする。その後は、良くなっては少しまた気を許し、疲れるぐらい仕事をすると風邪を引く、といった繰り返し繰り返し。先生にお世話になってから1年2ヵ月が過ぎた。
昨年の暮れ12月14日も風邪で咳と痰が出てきた。
「この状態では駄目だから、少し入院をして喘息を治しなさい。体を休めなくては」
と先生に言われたのですが、家の都合でとても入院はできないので、通院で点滴をして頂くようにお願いをした。その時は16日間続けてやっとピーピーがおさまって良かった。「私は薬が飲めないからやはりステロイドしかないのだ」と感じた。
しかし、この時完全によくなっていなかったのか1月10日頃からピークフローが上がらなくなって、自分でも「あれ? どうしたのか風邪も引いたようでもないが…」と思っていた。だんだん下がって2日目頃からまた咳と痰が出るようになり、やっぱり風邪だったのだとわかった。ところが4日目の朝から熱が出て39度もあり、ざわざわとしてきた。今日は先生の診察日だと思い、フラフラしながらも病院まで送ってもらった。先生の診察を受けるなりすぐそのまま入院となった。
《先に言われた時に入院すればよかったのに…》
といくら悔やんでも悔やみ切れなかった。入院は3週間におよんだ。入院中は、
《2年前薬害をおこし何も薬が飲めずあんなに苦しんでいたのを、やっといい先生に巡り会えて今ここまで良くなったのに…》
と自分ながら自分のことを悔やんでいる始末。入院する前はこれほどステロイドとは喘息になくてはならない薬とは思えなかった。それが入院していろいろ反省をしてみると、これほど私にはステロイドという薬は切らされないのだと。点滴も先に2本ずつ、後から1本になり、退院する3日前からは点滴は何もせず家で使っていた吸入ステロイドだけになったが、ピークフローが1日1日と上がってゆく。今回の点滴では前のようなひどい湿疹も出なかった。少しはかゆみはあったが前のように我慢できないほどではなかった。
→最初へ
この方の場合、総合病院に入院していたのですがあまり良くならず、退院したその足で私のもとを訪れました。この方からの手紙もいろいろな点で貴重な内容を含んでいると思います。
(1)まず、喘息の発症について。他の人の手記からも窺えることですが、決して喘息は、子供の頃からアレルギー体質のある人にばかり発症する病気ではなく、まったく喘息の素因がない人にでも起こりうる疾患であることは、喘息でない健康な人にも教訓になるかと思います。またその誘因が“風邪”が長引きこじらせたことにあることは非常に重要です。“風邪は万病のもと”、昔の人の言うことは決して間違っていないのだなと感心させられます。
(2)発作から意識を失い救急車で運ばれた様子は、とても貴重な情報を与えてくれていると思います。よく、“喘息死”という言葉を聞くことは多いと思いますが、ほとんどの喘息の患者さんは、自分と無縁のことと考えているのではないでしょうか? この方の場合、意識を失うその日に病院で点滴を受けているのです。それでも、発作から意識を失ってしまったです。おそらく粘稠性の痰が太い気道を閉塞し窒息してしまったのでしょう。この人の場合、家族の人がまだ寝ずに起きていたことが不幸中の幸いでした。もし、周囲に誰もいなければ、彼女は間違いなく“喘息死”に至っていたでしょう。決して脅かしているわけではありませんが、“喘息死”はいつも隣り合せであることを胆に命じて頂きたいと思います。
これと関連することですが、よくこのような状態で“喘息死”に至った人の状況を観察しますと、気管支拡張剤のスプレーを握り締めたまま亡くなっていることが多く、そのことから、気管支拡張剤の乱用は喘息死の引き金になるのではないかと考えられた時期がありました。もともと気管支拡張剤は心臓を刺激します。その乱用により心停止を来したことが“喘息死”の原因であると考えられたのです。よくアロテックやベロテックなどの気管支拡張剤の使用は1日3回までとか注釈を受けたことがある方は多いと思いますが、それはこの“喘息死”に対する配慮に由来するものと思われます。
しかし、最近では見解が違ってきています。つまり、気管支拡張剤を比較的大量に吸入で連用してもさほど心臓刺激性は少ないことが判明してきたのです。“喘息死”する患者さんは気管支拡張剤を過信するあまり、「吸入すれば大丈夫」と苦しいと何度も使用し、本来なら病院を受診すべきなほど病状が悪化しているのにその時期を失してしまう。そのうちにこの方のように痰をつまらせて窒息してしまう。死のぎりぎりの状態まで気管支拡張剤を使用しているわけですから、当然亡くなった患者さんは気管支拡張剤を握りしめているか、遺体の周辺に気管支拡張剤が転がっていたりする訳です。
私は、苦しい時は我慢しないで早目に気管支拡張剤を吸入するように指導しています。むしろ、我慢することが病状の悪化を招くからです。回数も特に制限を設けていませんが、大切なことは2、3回気管支拡張剤を吸入してもすぐ苦しくなる時は、早目に病院を受診し点滴を受けることなのです。
(3)あれほど大きな発作を起こし十分加療したはずなのに、退院6日目でまた発作を起こしてしまったこと。この点も実は喘息治療においてとても大切な内容を教えてくれているのです。
長期間入院して発作も起きず調子がよくなる。医師が診察をしても特に発作の兆候が見られない。だれも疑うことなく退院と考えます。しかし、この方のように退院してもまた発作を起こしてしまう。こんな時患者さんにとって再度発作で病院を受診することはとても辛いことではないでしょうか? たいていの患者さんは、医師や家族をがっかりさせたくないと思い、我慢してしまうはずです。
そして多少調子が悪くても、次の定期受診で先生から「どうですか?」と尋ねられると「大丈夫です」と言うでしょう。
しかし、このパターンこそいわば“昔風”の喘息治療なのです。つまり、退院の基準が、“発作”という自覚症状であった点が問題なのです。
誰しも、特に若い患者さんなどは、苦しいのが治まると早く退院したがるものです。しかし、苦しくないからといってすぐ退院するとまた発作を起こしてしまう。良くないことに一度退院してからの発作は、先ほどの理由で苦しさをこらえる訳ですから、状態は前より悪くなりがちです。ですから、いよいよ苦しくて再入院すると前よりも長くなってしまう。
これにはっきりと答えを出すことができるのがピークフローメーターなのです。少なくとも入院前の値を知っている患者さんなら、多少症状が良くなってもPF値が入院前の自己ベストに達していないと、安易に「退院させて下さい」とは、言わなくなります。
手紙では触れられていませんでしたが、実はこの方もそうだったのです。つまり、熱が出て発作が起きて病院に入院した訳ですが、この方も2週間の点滴で症状が大分良くなった時期があったのです。「あと何日ぐらいで退院できますか?」と聞いてきたことがありました。その時私は、「ちょっとピークフローを吹いてみて下さい」と、この方に吹いてもらいました。すると値は250でした。入院前の良い状態では400は吹けていましたから、250という不完全な値を知った彼女は、私が「まだまだだね。もう少し点滴しないとね」と言うとすぐ納得してくれました。
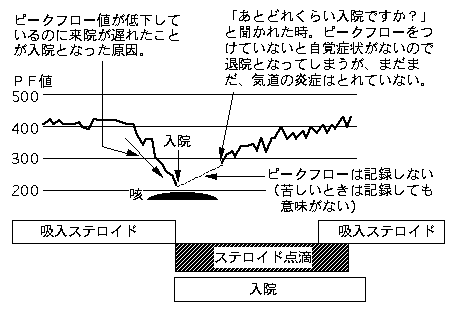
もし、この方もまた私自身もピークフローの有用性を認識していなかったら、どういう結末だったでしょうか? 400吹けていた人が250しか吹けていないのは、まだ気道に炎症が残っているからであり、逆にこのような時は十分なステロイドを投与していいし、またしなければならないのです。
(4)「どうすればいいのですか?」と聞いてみたら「死ぬしかないだろうな」と笑いながら話す先生。苦しい時にこんな一言は、忘れたくても一生忘れられるものではないでしょう。
大人はまだその辛い一言に反論したり、親しい人に打ち明けて憂さを晴らすことができるでしょう。しかし、もし子供だったらどうでしょうか? 子供は反論できる訳もなく、お茶を飲みながら「あの先生ひどいんだぜ」なんて悪口が言えるでしょうか? ほとんどは大きな“心の傷”として一生残ってしまうのではないでしょうか? 私がこの寄稿集で皆さんに訴えたい大きな問題点のひとつがこのことなのです。小児科の先生や喘息児を持つ両親は、ステロイドの弊害ばかりを気にして、なかなかステロイドを使おうとしない傾向があります。気管支喘息の何割かは大人になると治ると言われていますが、喘息を患っている時に受けた“心の傷”は一生癒えないのではないでしょうか?
(5)「喘息持ちは咳と痰が出るのは少しぐらい仕方ないなあ」と先生の諦めたような一言。この先生はおそらく喘息は専門ではないはずですから、喘息で咳と痰が出るのは当り前と思っているのでしょう。
私がここで取り上げたいのは、患者さんやその家族の方も同じような意識を持っていることが多いのではないか、という点なのです。よく「私は喘息だからあまり走れない」とか「私も喘息だから低気圧が接近したり寒い日などは調子が悪い」という訴えをよく耳にします。
しかし、“喘息だから”というのは“喘息の状態があまり良くないから”ということなのです。つまり、喘息であっても治療によって状態がよくなれば普通の人と同じように「全速で走っても何ともない」し、「低気圧が来ても寒くても調子は悪くならない」のです。
この良い例は(03)の患者さんです。彼女もPF値が400前後の時は、「(喘息だから)生理がくるとPF値が下がる」とか、「(喘息だから)いつも風邪をひいてしまう」とよく耳にしたものです。しかし、十分点滴をしてPF値が500を越え良い状態になるとどうでしょう、「生理でもPF値は下がらない」し、「風邪さえひかなくなった」ではありませんか? 「喘息持ちは咳と痰が出るのは仕方ない」と諦めているとすれば、もっと良くなるのに勿体ないとしか思えないのです。
喘息の考え方に関しては昔と今では大きな認識の違いがあります。恐らくその認識のずれが多くの誤解を生んでいると思われます。それは、昔は喘息は“発作が起こらなければ病気は安定している”と思われていましたが、最近はもっと進んで“普通の人と同じように生活できなければ病気は安定していない”と思われるようになってきたのです。この際、「自分は喘息だから…」という考えはもう卒業しませんか? (ただし、都合の悪い時は「自分は喘息だから…」と嫌なことを引き受けなくてすむ場合もありますが…。→(09)の患者さん参照。)
(6)吸入ステロイドを使うようになって1週間目、だんだん体が楽になってピークフローも380〜400ぐらいまで上がるようになり、先生の診察の時「このまま良くなるといいね」と言われて安心して帰った。ところが、しばらくした12月5日にまた風邪を引いてしまった。家族の誰かが風邪を引くと必ずうつってしまう…。この方のこれまでのPF値ベストは420から430位です。
私が「このまま良くなるといいね」
と言った本当の意味は、
「この位のPF値のまま何も症状がなく普通に生活ができるようになるといいね。でも、もしこの位の値でもちょっと無理をするとPF値が下がったりすぐ風邪をひいてしまうようでは、完全な状態ではないから、まだまだ治療しなければならないよ」
という意味なのです。(だったら最初からそう言って下さいと言われそうですが…。)本当は、もっとPF値は上がるはずだと思っていましたし、案の定完全な状態ではなかったためか、すぐ風邪をひいてしまったようです。実際この手紙の中でも
「その後は、良くなっては少しまた気を許し、疲れるぐらい仕事をすると風邪を引く、といった繰り返し繰り返し。先生にお世話になってから1年2ヵ月がたった」
と書かれています。本人はおそらく以前の苦しい時に比べれば、風邪をひくぐらいで無理ができるようになったのだから満足である、との意味なのでしょう。しかし、終いには発作で入院となってしまいました。
400前後の値はまだまだ不十分であり、もっともっとPF値が上昇する余地はあるのです。“発作のない状態”から“人間らしい生活”へ、これが新時代の喘息治療の目標であり、またこの状態に自分を置いておくことが、発作からは程遠い状態に自分を置いておくこと、すなわち“発作予防”になるのです。
(7)PF値がだんだんと低下し熱が出てついには入院となったことが詳しく書かれています。この時私が口をすっぱくしてこの方に注意したことは、私が週に1度しか出張していなかったこともありましたが、私が来るまでの1週間を我慢していたことは最もいけないことだということです。病院には常勤の医師がいる訳ですから、早目に来院して点滴を受けるべきでした。私がこの時診た状態は、もう少し遅かったら最初に入院した時のようになっていたかもしれないくらい危ない状況であったのです。喘息は我慢しては絶対いけません。早目早目に手を打つことを是非覚えて下さい。1週間来院が遅れたから3週間も入院になったのです。あと3、4日早ければ入院しなくても済んだのです。
(8)「先に言われた時に入院すればよかったのに…」早目の入院を勧めた私が言うのもおかしな話ですが、気持ちは良くわかるつもりです。「夫が身体が不自由で付き添ってあげなくてはいけない」、「仕事が忙しくて自分がいないとどうにもならない」、「子供が受験で入院できない」などなど…。
喘息が良くならない患者さんの中には、いろいろな理由で入院できず、“喘息死”と背中合わせのぎりぎりの生活を送っている方はたくさんいます。しかし、自分がいなければ誰がやるという状態だからこそ、身体を大切にしなければならないのではないでしょうか? もしそのような状態で大発作で倒れてしまったら、それこそ誰が夫や子供、あるいは仕事の面倒を見てくれるのでしょうか?
最近は、デイケアサービスなど付き添いの人の負担を一定期間和らげてくれる制度があります。また、結局大きな発作で入院となっても、誰かが仕事の代わりを務めてくれたり、受験生だって結構一人で何でもできるものです。
むしろ、周りの人のことを考えてみて下さい。「自分がいなければ」と無理をしてひどい咳をしながら、仕事をされたり勉強の付き添いをされたのでは、周囲の人の方が迷惑というものです。いつ大発作が起きるかもしれないと仕事や勉強に身が入らないでしょう。それよりは、とにかく一度すっかり良くしてもらって、良くなったらまた頑張ってもらおうと考えるのが普通ではないでしょうか?
私が入院を勧めた患者さんの中には、よく「自分がいないとご飯出しができないので絶対入院はできない」と言う方がいるのですが、家族の方がむしろ「ご飯は自分たちが何とかするから、入院して良くしてもらったら?」と理解がある場合があったり、またそう言っている割には(私には相談なしに)平気で家を空けて2〜3泊の温泉旅行に行ったりする場合(この場合は不十分な状態での外泊なので非常に危険)があります。
そう考えると、喘息で良くならない人は良く言えば“自分の身体を顧みない”性格、悪く言えば“自分よがりで他人を信じない”性格の人が多いという気がしてきます。もっともっと周囲の人を信用して下さい。借りは良くなったら何倍にしてでも返せるはずです。
誰だって入院なんかしたくないのです。でも考えて見て下さい。早く入院すれば10日から2週間で(しかもすっかり)良くなるのに、その期間を惜しむあまり無理をして病気をぎりぎりまで我慢してついには大きな発作を起こし、結局1、2ヵ月を失ってしまう患者さんの多いこと。このような入院では大きな発作を起こしても“喘息死”に至らなかっただけまだ良いと考えなくてはならないし、また完全に良くなるならいいですが、病気というのはこじれればこじれるほど治りにくくなり後遺症も多くなるものなのです。
私も十分意地が悪いと思いますが、言っても聞かない患者さんが、ついには発作を起こして入院してくると、「なんだ、入院できるんじゃない?!」と皮肉を言ってしまうことがあります。でも、皆さんのことを考えたあげくの皮肉ですから許して下さい。必ずその皮肉をカバーしておつりが来るくらいのことはしてあげますので…。
(9)最後に、この方への“主治医からの一言”は一言でなくなってしまいました。重箱の隅をつつくようで大変失礼なことを並べてしまいました。その点は心よりお詫び申し上げますが、でもこの方の手紙は他の患者さんへ喘息治療をどうしたら良いかを教えるのに、大変意味のあるとても良いことがたくさん書かれているのです。一生懸命書いて下さって本当にありがとうございました。
→最初へ
・初めての薬には気をつけよう(平成10年8月18日)。
その後、450くらいのピークフロー値で安定した状態を保っていたのですが、先日大変なエピソードがありました。
ひどい頭痛がするので、脳卒中ではないかと脳外科専門の近医を受診したところ、風邪との診断で、抗生物質と消炎剤を処方されたのです。いずれも彼女にとっては初めて服用する薬でした。彼女はある種のステロイドにさえ薬疹を生じるくらいのひどい薬剤アレルギーで、私は普段から「もし風邪を引いたら、風邪薬は服用せずに喘息が悪化しないように副作用のないステロイドを点滴するように」と指示していたのですが、よほどの頭痛に仕方なく処方された薬を服用してしまったのです。どちらが原因かは分かりませんが、彼女は次第に意識がなくなり救急車のお世話になってしまいました。この間、息苦しいという症状もなく、また退院時のピークフロー値も以前と同じ位吹けていましたので、アスピリン喘息とはどうも考えにくいのです。
彼女は幸い一命を取り留めましたが、皆さんも新しい薬剤を服用するときは細心の注意を払って下さい。ましてやこれまでアスピリン喘息のような既往のある方は当然です。もし、やむなく服用する場合は、必ず家族などの人前で「飲むよ」と宣言してから服用し、しばらくは様子を見てもらいましょう。一人で意識を失ったら助かる見込みはありません。
→最初へ