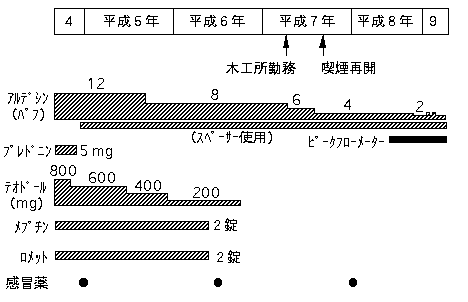
僺乕僋僼儘乕抣偵墳偠偰媧擖僗僥儘僀僪夞悢傪寛傔偰偄傞丅
<1>偳傫側帪偵敪嶌偑偁傞偐
丒夁楯丗崱偼偙傟偑堦斣偺尨場丄偙傟偑柍偄応崌偼懠偺尨場偑偁偭偰傕丄偨偄偰偄敪嶌偼婲偒側偄丅
丒嬻婥丗僞僶僐偺墝(晹壆偵偙傕偭偨応崌)丅幵偺攔婥(岎捠検偺懡偄摴楬丄戝宆幵偺屻傪偟偽傜偔憱偭偨帪)丅
丒夁怘丗堓偑攛傪埑敆丄暃岎姶恄宱偺嫽暠丅
丒偙傟傜偑廳側傞偲梉怘屻偵敪嶌偑巒傑傞偙偲偑偁傞丅偁傞偄偼梻挬懅嬯偟偔偰栚妎傔傞丅
<2>擔忢偺懳嶔
丒夁楯傪旔偗傞(偲偼尵偭偰傕擄偟偄)丅
丒晹壆偺姺婥偵拲堄偡傞丅壞偺椻朳偼側傞傋偔旔偗傞丅
丒悈暘傪廫暘偵庢傞(偡偖偵攔煏偡傞偙偲偵側傞偑)丄偨偄偰偄偼偍拑(僇僼僃僀儞偑偄偔傜偐岠偔傛偆偩)傪堸傓丅敪嶌偺挍岓偺抜奒側傜丄偙傟偱惷偐偵偟偰偄傞偲30暘(挿偔偰傕1帪娫)埲撪偵帯傑傞丅
丒1擔侾夞(栭)僺乕僋僼儘乕傪寁傞(偳偺偔傜偄偺挷巕偐丄戝懱帺暘偱傢偐傞偺偱栭1夞偩偗偱娫偵崌傢偣偰偄傞)丅偙傟偲梻擔偺梊掕丄揤岓側偳傪峫偊崌傢偣媧擖僗僥儘僀僪偺検傪寛傔偰媧擖(1擔偱偙偺帪1夞偺傒0乣4僷僼)丅
丒偨傑偵婥偑岦偔偲1擔悢夞僺乕僋僼儘乕儊乕僞乕傪巊偆丄偙傟偱帺暘偺帺妎抣偺廋惓傪偟偰偍偔丅
丒偦偺懠丄敪嶌偵偄偨傜側偄挍岓偺抜奒偱憗栚偵懳嶔傪庢偭偰偄傞偮傕傝偱傕丄偮偄柍棟傪偟偨傝桘抐傪偟偰敪嶌傪婲偙偡偙偲傕偁傞丅偦傫側帪偵偼忋偵弎傋偨傛偆偵悈暘傪廫暘偵庢傝埨惷傪曐偮丅偦傟偱傕偩傔側傜(崱側傜偨偄偰偄丄偦偺慜偵梊應偑偮偔偺偱弶傔偐傜)懍峌惈偺媧擖嵻(僗僩儊儕儞D)傪巊偆丄偙傟側傜5暘乣10暘偱岠壥偑尰傢傟傞(偄偞偲側傟偽偙傟偱娫偵崌偆偙偲偵傛傞埨怱姶偼憡摉戝偒偄偺偱丄奜弌帪偵傕帩偪曕偔)丅1夞偱晄懌側傜傕偆1夞丅偟偐偟偙偙傑偱廳偄偺偼嵟嬤偱偼寧偵1夞偁傞偐側偄偐丅婰榐傪尒傞偲丄崱擭偼傑偩1夞傕柍偟丅
<3>敪嶌偑廳偐偭偨崰
丒敪嶌偼梉曽偐傜栭偵偐偗偰廳偔側傞丄偙傟偱偖偭偡傝柊傟側偔側傞丄旀傟偑庢傟側偄丄傑偡傑偡敪嶌偑廳偔側傞偲偄偆埆弞娐丅栭拞偵懅嬯偟偔偰栚妎傔丄媧擖偟(摉帪偼僱僽儔僀僓乕傕巊梡)傑偨怮傞傑偱1帪娫偔傜偄偐偐偭偨丅姦偄婫愡偵偼摿偵偮傜偐偭偨丅
丒偦傫側忬懺偐傜扙偟丄挬傑偱柊傟傞傛偆偵側傞偲丄偨偲偊挬懅嬯偟偔偰傕栚妎傔傞偺偱傕丄偩偄傇妝偵側偭偨傛偆偵姶偠偨丅
丒偳偺傛偆偵敪嶌偑婲偒傞偺偐丄栻偼偳偆岠偔偺偐丄偦偆偄偭偨偙偲偑偁傞掱搙傢偐偭偰偒偰帺暘偱僐儞僩儘乕儖偱偒傞傛偆偵側傞偲丄偦傟偲偲傕偵夣曽偵岦偐偭偨丅
丒弶婜偺崰偐傜偙傟傜偺偙偲偑傕偭偲娙扨偵暘偐偭偰偄傞偲丄偁傟傎偳廳偔傕側傜偢丄挿堷偒傕偟側偐偭偨偐傕偟傟側偄丅姵幰偺棫応偐傜偡傞偲丄帺屓娗棟偱偒傞偐偳偆偐偑嵟傕廳梫偱丄偙傟偼敪徢梫場偺傂偲偮偱偁傞偲尵傢傟偰偄傞怱棟揑梫場偺柺偐傜偟偰傕戝帠側帠偱偼側偄偐丅偳傫側昦婥偱傕丄姵幰偑帺暘偱帯傞婥偵側傜側偄偲側偐側偐帯傜側偄丅
丒偦傫側傢偗偱丄歜懅偺徢忬丄尨場丄宱夁丄栻丄攛偺夝朥妛側偳堦斒揑側偙偲(姵幰傂偲傝傂偲傝偵屌桳偺偙偲偼宱尡偺拞偱尒偮偗偰偄偔偲偟偰)偵偮偄偰丄姵幰偺懁偐傜抦傞偙偲偑偱偒傞杮側傝僔僗僥儉側傝偑桳傞偲椙偄丅尰嵼偺擔杮偺堛妛彂偼丄偁傑傝偵傕偼偭偒傝偲堛幰岦偗偲姵幰岦偗偵暘偐傟夁偓偰偄傞傛偆偵姶偠傜傟傞丅
<4>僗僥儘僀僪偺暃嶌梡
丒摿偵姶偠偨偙偲偼側偄偑丄媧擖僗僥儘僀僪偺巊偄偼偠傔僲僪偵巋寖姶偑桳偭偰丄偐偊偭偰敪嶌偺偒偭偐偗偵側偭偨偙偲偑偁傞丅愩戂丅僗僥儘僀僪偵尷掕偟偨偙偲偱偼側偔媧擖慡懱偺偙偲偐傕偟傟側偄偟丄栻偺偣偄偱偼柍偄偐傕偟傟側偄偑丅
丒堛巘偺娫偱僗僥儘僀僪偵懳偟偰偝傑偞傑側堄尒偑偁傞(戝惃偼傎傏孹偄偨傛偆偩偑)偙偲偼暘偐傞偑丄忋偵弎傋偨傛偆偵姵幰偺棫応偐傜偼丄偦傟偑偳偆偄偆偙偲側偺偐娙扨偵偼暘偐傝偵偔偄丅
<5>偦偺懠
丒姰慡偵偱偼柍偄偵偟偰傕丄偁傞掱搙僐儞僩儘乕儖偱偒傞傛偆偵側偭偨偺偼丄媧擖僗僥儘僀僪嵻偺岠梡側偺偼妋偐丅
丒僐儞僩儘乕儖偱偒傞傛偆偵側偭偰偐傜偼丄帺屓娗棟偱偒傞昦婥傪1偮帩偭偰偄傞偙偲偺棙揰(偙傟傪棟桼偵偟偰柍棟傪旔偗偨傝丄抐傢偭偨傝偱偒傞帠傕偁傞)偝偊姶偠傜傟傞傛偆偵側偭偨丅
搤偵擖偭偰偐傜巇帠偺曽偑朲偟偔側傝丄尰嵼旀傟偑偨傑傝偓傒偱丄側偐側偐帪娫偑庢傟偢抶偔側傝傑偟偨偑丄偲傝偁偊偢巚偄晅偄偨偲偙傠傪彂偄偰傒傑偟偨丅
仺嵟弶傊
偙偺曽偼彫帣歜懅偺婛墲偑偁傞曽偱偟偨偑丄暯惉3擭傛傝傗偼傝晽幾偑尨場偱敪嶌偑傂偳偔側傝丄2夞偺擖堾楌偑偁傝傑偟偨丅巹偑恌傞傛偆偵側偭偨帪揰偱偼丄媧擖僗僥儘僀僪偺懠偵丄僥僆僪乕儖(100mg)8忶丄儊僾僠儞2忶丄儘儊僢僩2忶丄僾儗僪僯儞(5mg)1忶傪暈梡偟偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄徢忬偑埨掕偟偰偄偨偺偱丄傑偢僾儗僪僯儞傪巭傔僥僆僪乕儖傪抜奒揑偵尭傜偟丄暯惉6擭拞崰傛傝杮恖偲廫暘榖偟崌偭偨寢壥丄偡傋偰偺撪暈傪拞巭偟丄媧擖僗僥儘僀僪偺傒偱歜懅傪僐儞僩儘乕儖偡傞偙偲偵偟偨偺偱偡丅
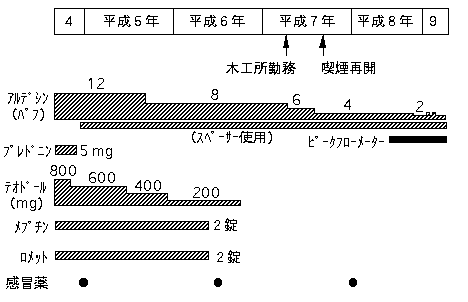
偦偺屻偺宱夁偼弴挷偱丄媧擖僗僥儘僀僪傕1擔侾2媧擖偐傜8媧擖仺6媧擖仺4媧擖偲尭検偵惉岟偟傑偟偨丅偝傜偵丄暯惉8擭偐傜偼僺乕僋僼儘乕婰榐傪奐巒偟丄僺乕僋僼儘乕偑掅壓偟偨傜揔媂媧擖僗僥儘僀僪傪憹尭偡傞姰慡側乬帺屓娗棟懱惂乭偵堏峴偟偨偺偱偡丅枅擔偦偺栭偺僺乕僋僼儘乕抣傪嶲峫偵媧擖僗僥儘僀僪偺検傪寛掕偡傞偲偄偆曽朄偼旕忢偵儐僯乕僋偱偁傝丄惀旕懠偺曽傕嶲峫偵偟偰梸偟偄偲巚偄傑偟偨丅埲壓偵偦偺堦晹傪徯夘偟偰偍偒傑偡丅
擔晅 |
揤岓 |
挬 |
梉 |
栭 |
媧擖夞悢 |
12寧1擔 |
愥 |
丂 | 丂 | 576 |
4媧擖 |
2擔 |
愥 |
丂 | 588 |
丂 | 4媧擖 |
3擔 |
撥 |
519 |
丂 | 540 |
4媧擖 |
4擔 |
撥乛塉 |
丂 | 605 |
丂 | 2媧擖 |
5擔 |
塉 |
丂 | 丂 | 應掕偣偢 |
媧擖偣偢 |
6擔 |
撥乛塉 |
丂 | 丂 | 620 |
2媧擖 |
7擔 |
惏 |
丂 | 丂 | 應掕偣偢 |
媧擖偣偢 |
8擔 |
撥乛塉 |
丂 | 607 |
丂 | 2媧擖 |
9擔 |
塉 |
521 |
丂 | 581 |
4媧擖 |
600傪挻偊偨傜2媧擖丄600傪壓夞偭偨傜4媧擖偲帺暘側傝偵栚埨傪嶌偭偰偄傞偺偑傢偐傞偲巚偄傑偡丅傑偨怓乆側帠忣偱丄帪乆偼應掕傗媧擖傪偟側偄帪偑偁傝傑偡偑丄偙傟偼恖娫偱偡偐傜巇曽側偄帠偩偲巚偄傑偡丅偟偐偟丄匘偺彈巕崅惗傕弎傋偰偄偨傛偆偵丄僥僆僪乕儖側偳偺婥娗巟奼挘嵻偲堘偭偰丄昦忬偑埨掕偟偰偔傞傛偆偵側傞偲媧擖僗僥儘僀僪偺応崌偼1夞偖傜偄朰傟偨偐傜偲偄偭偰偡偖敪嶌偑婲偒傞栿偱偼偁傝傑偣傫丅戝愗側偙偲偼丄2丄3擔媥傫偱偟傑偭偨偐傜傕偆偄偄傗偲偁偒傜傔偢偵丄彮偟偖傜偄朰傟傞偙偲偼偁偭偰傕挿偄栚偱懕偗傞偙偲偱偡丅
傛偔丄媧擖僗僥儘僀僪傪偟側偔偰傕丄敪嶌偑婲偒側偄偐傜傕偆偡偭偐傝椙偔側偭偨偲帺屓敾抐偟偰偟傑偆曽偑偄傑偡丅偟偐偟丄僺乕僋僼儘乕傪偮偗偰偄側偄偲丄嬯偟偔偼側偄偗傟偳傕師戞偵婥摴墛徢偑嵞擱偟丄晽幾傪堷偄偨傝偟偨嵺偵傑偨昦堾庴恌偑昁梫偲側傞傛偆側敪嶌偑婲偒偰偟傑偆偺偱偡丅
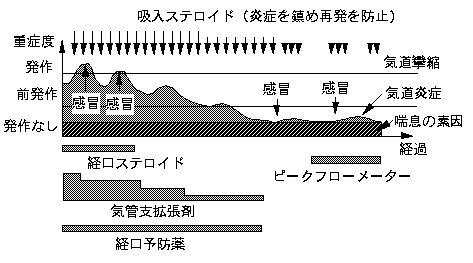
僺乕僋僼儘乕傪偮偗偰偄側偄偲傛偔丄乽椙偔側偭偨偲巚偭偰栻傪巭傔偰偄偨偺偵晽幾傪堷偄偨傜媫偵敪嶌偑婲偒偨乿偲偄偆傛偆側偙偲傪偍偭偟傖傞姵幰偝傫偑偄傑偡丅偟偐偟丄偙傟偼寛偟偰媫偵埆偔側偭偨偺偱偼側偔丄師戞偵埆偔側偭偰偄傞偺偱偡丅僺乕僋僼儘乕傪婰榐偟偰偄傟偽偙偺夁掱偑椙偔傢偐傞偺偱偡丅偙偆側傞偲丄帯椕偼傑偨嵟弶偐傜傗傝捈偟偵側偭偰偟傑偄傑偡丅偝傜偵偼丄偙偆偟偨傂偳偄敪嶌傪壗搙偐孞傝曉偡偙偲偱歜懅偼師戞偵偟偐傕妋幚偵埆壔偟帯傝偵偔偔側傞(擄帯壔)傕偺側偺偱偡丅偱偒傟偽栻傪堦愗拞巭偟偨偲偟偰傕丄僺乕僋僼儘乕偩偗偼堦惗偮偗懕偗傞偙偲傪偍姪傔偟傑偡丅偙傟偑歜懅偲偆傑偔偮偒偁偆曽朄偩偲巚偄傑偡丅
埲慜丄歜懅偺尋媶夛偱丄巹偑丄
乽偨偲偊媧擖傗搳栻傪拞巭偟偰傕丄偱偒傟偽堦惗僺乕僋僼儘乕婰榐傪懕偗傞傋偒偩乿
偲敪尵偟偨嵺丄偁傞彫帣壢偺愭惗偐傜丄
乽偦傟偱偼丄巕嫙偺応崌丄堦惗歜懅偲偄偆昦婥偐傜摝傟傜傟偢丄惛恄塹惗忋傕椙偔側偄偺偱偼側偄偐丠乿
偲偺庡巪偺幙栤傪庴偗偨偙偲偑偁傝傑偡丅偙偺愭惗偑尵偄偨偐偭偨偙偲偼嫲傜偔丄
乽乬歜懅亖敪嶌乭偱偁傞偐傜丄嬯偟偄昦婥偺偙偲偑摢偐傜偄偮傕偼側傟側偄偺偼丄巕嫙偺敪堢忋傕惛恄塹惗忋傕栤戣側偺偱偼側偄偐丠丂巕嫙偺応崌丄枅擔僺乕僋僼儘乕傪偮偗傞偲尵偭偰傕梀傃偵柌拞偵側偭偰婰榐傪朰傟傞偙偲傕懡偄偟丄偦傫側帪偁偨偐傕廻戣傪朰傟偨傛偆偵恊傗愭惗偐傜幎傜傟偨偺偱偼偨傑傜側偄丅巕嫙偺応崌丄栻偝偊偒偪傫偲堸傫偱偄偰敪嶌偑婲偒側偗傟偽丄僺乕僋僼儘乕抣偺曄摦偵堦婌堦桱偡傞傛傝傕丄歜懅偺偙偲偼朰傟偰怢傃怢傃偲帺桼偵偝偣偨曽偑椙偄偺偱偼側偄偐丠乿
偲偄偆堄枴偩偲巚偄傑偡丅偟偐偟丄媧擖僗僥儘僀僪傪拞巭偟偰偟偽傜偔偼埨掕偟偰偄傞傛偆偱傕丄柍棟傪偟偨傝晽幾傪堷偄偨傝偡傞偲寢嬊敪嶌偼婲偒偰偟傑偄傑偡丅傑偨丄偄偮敪嶌偑婲偒傞偐傕偟傟側偄丄偩偐傜塣摦傕偱偒側偄偟丄墦弌傕偱偒側偄偲偄偆晄埨側忬懺偑懕偔偺偱偼丄偦傟偙偦惛恄塹惗忋栤戣側偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠丂巹偼丄歜懅偱嬯偟偄帪偙偦歜懅偺帠傪朰傟傞傋偒偱偁傝丄媡偵挷巕偺椙偄帪傎偳帺暘偑歜懅偱偁傞帠傪朰傟傞傋偒偱偼側偄偲偄偆峫偊傪傕偭偰偄傑偡丅廬偭偰丄僺乕僋僼儘乕傪婰榐偟懕偗傞偙偲偼丄寛偟偰歜懅偺埫偄僀儊乕僕偲偮偒偁偆偙偲偱偼側偄偲巚偆偺偱偡丅
(16)偱徯夘偡傞彫妛3擭惗偺彈偺巕側偳偼丄僺乕僋僼儘乕傪偮偗傞偺偑妝偟偔偰巇曽偑側偄偲尵偄傑偡丅枅擔婰榐偡傞偙偲偱丄帺暘偺挷巕偑傛偔傢偐傝惗妶偵帺怣偑傕偰傞偲偄偆偺偱偡丅枅擔敪嶌偑婲偒傞傛偆側忬懺偱僺乕僋僼儘乕抣傪寁應偟丄埆偄抣傪尒偰枅擔婥暘偑埫偔側傞偲偟偨傜丄偦傟偼惛恄塹惗忋戝栤戣偱偟傚偆偑丄偦傫側忬懺偱偼婰榐偡傞堄枴偑偁傝傑偣傫丅偦偺忬懺偐傜扙媝偡傞偨傔偵僺乕僋僼儘乕傪偮偗傞昁梫偑偁傞偺偱偡丅僺乕僋僼儘乕偼椙偄忬懺偺帪偵偙偦婰榐偡傋偒傕偺側偺偱偡丅
乬歜懅偲偆傑偔偮偒偁偆乭乗偙偺曽偑尵偆傛偆偵丄歜懅偲偄偆棟桼偱寵側偙偲偼嫅斲偱偒傑偡偟丄傑偨堦偮偺昦婥傪娗棟崕暈偡傞偙偲偼丄懠偺昦婥偵側傝偵偔偄偲傕尵偊傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠丂丂傛偔丄崱傑偱1搙傕昦堾偵偐偐偭偨偙偲偑側偄恖傎偳丄昦婥敪尒偑抶傟偙偠傟偰柦庢傝偵側偭偨傝丄偁傞偄偼戝昦偑塀傟偰偄偨傝偲偄偭偨偙偲偑偁傝傑偡丅傓偟傠丄寣埑偑崅偄偲偐丄崢偑捝偄偲偐偱偪傚偔偪傚偔昦堾偵偐偐偭偰偄偨曽偑丄憗偔昦婥偑尒偮偐傝揔愗側張抲傪偲偭偰傕傜偊偨傝偡傞丅乽壗偱帺暘偽偐傝歜懅偱偙傫側偵嬯偟偄巚偄傪偟側偗傟偽側傜側偄傫偩乿偲峫偊傞傛傝丄乽歜懅偼恄條偑帺暘偵庼偗偰偔傟偨憽傝傕偺乿偲慜岦偒偵峫偊偰丄偆傑偔歜懅偲偮偒偁偭偰丄帺暘偺寬峃娗棟傪偟偰峴偔偺傕堦偮偺惗偒曽偱偁傞偲巚偆偺偱偡丅
偙偺曽偼丄帺屓娗棟偑偱偒傞傛偆偵側偭偰丄栘岺強嬑柋偲偄偆歜懅偵偲偭偰嵟埆偲傕偄偊傞娐嫬偺怑応偵揮怑偟傑偟偨丅偝傜偵丄偙傟偼梋傝娊寎偱偒傑偣傫偑丄敪嶌偺堊偵偣偭偐偔傗傔偰偄偨墝憪傑偱傕彮側偄杮悢傜偟偄偺偱偡偑嵞奐偟偨偲偄偆偺偱偡丅偟偐偟丄偙傟偱戝偒側敪嶌傪婲偙偝偢偵偟偐傕PF抣傪600慜屻偵堐帩偱偒傞偺偱偡偐傜丄偦偺帺屓娗棟朄偵偼摢偑壓偑傝傑偡丅(偟偐偟丄偱偒傟偽偨偽偙偼巭傔偨傎偆偑傛偄偲巚偄傑偡丅歜懅偼崕暈偱偒偰傕攛娻偵側傞偐傕偟傟傑偣傫傛乧)
歜懅偺杮偼梋傝偵傕堛幰岦偗偲姵幰岦偗偵暘偐傟偡偓偰偒偰丄恀偺堄枴偱歜懅偺昦懺偑傢偐傜側偄丄偲偺巜揈偼側傞傎偳偲巚偄傑偟偨丅偙偺曽偺応崌丄妋偐偵帺暘側傝偵歜懅偺昦懺傪怓乆偲曌嫮偟丄怓乆側妏搙偐傜帺屓暘愅傪堦惗寽柦偟偰偄傞偐傜偩偲偼巚偄傑偡偑丄歜懅偺杮幙偑傢偐偭偨偙偲偱偼偠傔偰帺屓娗棟偑偱偒傞傛偆偵側偭偨柾斖椺偱偁傞偲巚偄傑偡丅乬歜懅偼抦傟偽晐偔側偄昦婥乭偱偡丅傕偭偲傕偭偲歜懅偵偮偄偰傢偐傞傛偆偵側傟偽丄昦婥偼崕暈偱偒丄偟偐傕寬峃幰偲壗傜曄傢傜側偄惗妶偑憲傟傞傛偆偵側傞偼偢偱偡丅奆偝傫傕惀旕偙偺曽偐傜歜懅娗棟朄偺僸儞僩傪偮偐傫偱梸偟偄偲巚偄傑偟偨丅
仺嵟弶傊